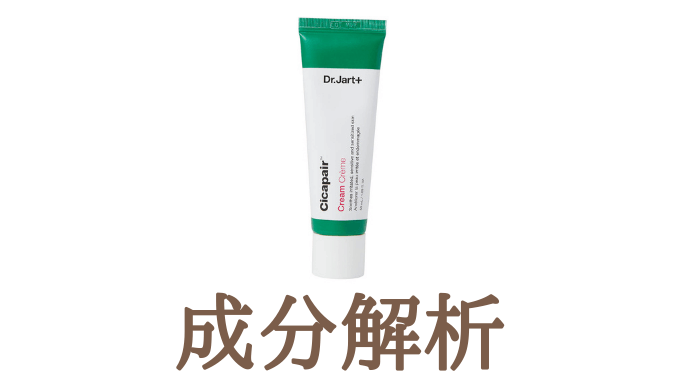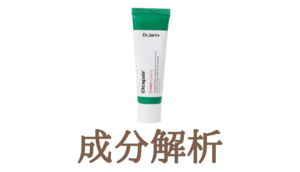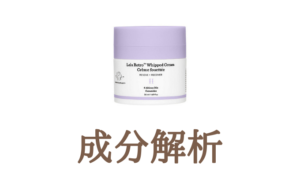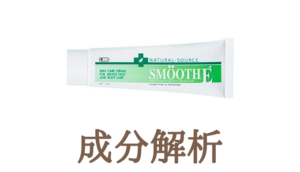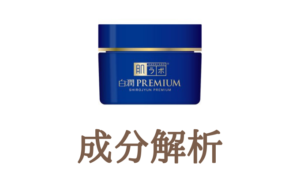こんにちは。コスメコンシェルジュエージェンシー(日本化粧品検定1級)のありす(@alice_kaiseki)です✨
今回は「シカクリーム」の代名詞とも言われる人気の韓国コスメ「ドクタージャルト シカペアクリーム」の成分解析です。
【はじめての方必読】当サイトの成分解析について
- 成分分解析は各成分の一般的な配合目的を記載したもので、製品の効果効能を保証するものではありません。
- 一部のコスメは、ブログ(可愛くなりたい)にて、レビューを掲載しています。
- リニューアル等により全成分が変更される可能性があります。見つけた場合はお問い合わせフォームから教えて頂けると助かります。
ドクタージャルト シカペアクリームの成分解析
まずこのコスメ「公式サイトと箱で全成分表示が違う」という問題があります。
どれが正しいのかは、正直わからないところ。「箱の成分が違ったら回収騒ぎだから箱の方が正しい」という意見もありますが、箱の表記は英語なので、なんとも言えません。
今回は、@コスメショッピングに掲載されていた成分を見て解析していきたいと思います。
第1世代、第2世代で成分が異なる
シカクリームとして有名なこの商品ですが、実は一度リニューアルをしており、第2世代の方が美容成分の量が多くなっています。

パッケージで見分ける方法は
- 第2世代の方がキャップが大きい
- 第2世代の方が「Cicapair」の文字が小さい
- 赤字の文字が第1世代は「Cream」、第2世代は「Cream Creme」
といった違いがあります。
今回の解析は、第2世代の全成分表示を見ています。
ベースは水分多めでさっぱり
ベースとなる保湿成分はBGとプロパンジオールです。
BGはさっぱり系で低刺激な保湿成分。
プロパンジオールもさっぱり系ですが、抗菌作用があります。この場合は濃度が高いので、若干刺激のリスクがあるかも。(その分パラベンやフェノキシエタノールを入れない設計になっています)
一般的なクリームに比べると、油分が少なく、水分が多めの構成になっていますね。
肌にフタをして水分蒸発を防ぐエモリエント作用は弱めですが、ベタつきにくく、さっぱりした仕上がりになります。
グリセリンも入っていないので、毛穴やニキビに悩む方にも相性が良いです。
コンセプトの成分は「ツボクサ系」
シカクリームというのは、ツボクサ系の成分を配合したコスメです。
ドクタージャルト シカペアクリームの場合は「ツボクサ葉エキス」「ツボクサエキス」「マデカツソシド」「アシアチコシド」「アシアチン酸」「マデカシン酸」が該当する成分ですね。
ツボクサはインドの伝統医薬学・アーユルヴェーダで皮膚、神経、血液の機能改善に有効であると言われ使用サれてきました。
化粧品の場合だと、抗炎症、抗酸化、保湿、血行促進、ターンオーバー促進、コラーゲン生成促進などの作用があると言われています。
一般的に化粧品に配合される植物エキスって作用はそんなに強くないんですが、ツボクサは濃度が高ければ、そこそこ強めの整肌作用を発揮してくれそうな成分です。
抗炎症・抗菌系の美容成分が多め
ツボクサエキス以外にも、植物エキスがたくさん入っています。
数が多いので、ひとつひとつの説明は省きますが、抗炎症や抗菌作用があると言われている植物が中心です。
あとは特徴的なのは「エリンギウムマリチムムカルス培養液」「ナイアシンアミド」「ストレプトコッカスサーモフィルス培養物」「アデノシン」「パンテノール」あたりかな。
- エリンギウムマリチムムカルス培養液・・・植物幹細胞エキス。保湿・引き締め系。
- ナイアシンアミド・・・シワ改善。コラーゲンや肌のバリア機能をサポートするエイジングケア成分。
- ストレプトコッカスサーモフィルス培養物・・・発酵乳酸菌。肌荒れや乾燥肌に働く成分。
- アデノシン・・・表情筋の伸縮を防いだり、コラーゲンをサポートする成分。
- パンテノール・・・保湿、抗炎症、傷跡ケアなどの作用あると言われている成分。
美容成分の中でも、機能性が高いと言われているものが多いですね。
おそらく濃度は高くないし、はっきり効果が得られる保証はありませんが、エイジングケアコスメでも人気の良い成分です。
あくまでも「化粧品」だから作用は強くない
ネット上でのシカクリームの口コミを見ていると「肌荒れが一晩で治った」「肌がすぐに白くなった」という意見もありますが、シカクリームはあくまでも化粧品。
成分が強めなので、人によっては効果が出やすいコスメではありますが、強い即効性は期待できません。
そもそもそんなにすぐに効果が出るのなら、誰も肌荒れに悩みませんよね・・・💦
ただし作用が強めの成分が入っているので、国産の優しい保湿成分メインのコスメに比べたら、それなりに効果は期待できるんじゃないでしょうか。
作用が強い=リスクもある
作用が強めの植物エキスなどが多く入っているコスメですが、作用が強いということはリスクもあります。
特にドクタージャルト シカペアクリームは植物エキスの種類が多く、抗菌や収れん作用のあるものが多く入っています。
なのでアレルギーや刺激のリスクが高い、ハイリスク・ハイリターンなコスメです。
敏感肌の人やアレルギー体質の人にはおすすめ出来ないし、そうでなくても初めて使う時は顔以外でパッチテストをした方が良いと思います。
調整系の成分
海外のコスメって、美容成分以外の、乳化剤やテクスチャの調整、浸透系などで、刺激性が強めの成分が使われていることがけっこう多いんです。
ドクタージャルト シカペアクリームはそういった刺激が強めの成分はほとんど入っていません。
合成香料・合成着色料・エタノールフリーで、乳化も低刺激な非イオン界面活性剤を使用しています。
まぁ植物エキスの抗菌作用による刺激やアレルギーのリスクがあるので、敏感肌向けとは言えませんが、それ以外の部分でいうと、日本のコスメに近い構成になっています。
成分解析のまとめ
- 油分が少なめで、水分が多い、さっぱり系のクリーム
- ツボクサをはじめとした肌荒れケア系の成分がたくさん入っている
- 抗菌・収れん作用を持つ植物エキスが多いので刺激のリスク高め
- 植物エキスの種類が多いから、肌に合わない成分もあるかも
- 国産の優しいクリームよりは、強い作用が期待できる
全成分と配合目的(予想)
| 成分名 | 目的 | 評価 |
|---|---|---|
| 水 | ベース | |
| BG | ベース(保湿) | |
| プロパンジオール | ベース(保湿・抗菌) | △ |
| エリンギウムマリチムムカルス培養液 | 植物性幹細胞培養液(保湿) | |
| トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | エステル油(エモリエント) | |
| セテアリルアルコール | 高級アルコール(調整・乳化補助) | (旧) |
| 水添ポリ(C6-14オレフィン) | 炭化水素油(エモリエント) | |
| エチルヘキサン酸セチル | エステル油(エモリエント) | |
| ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| シア脂 | 油脂(エモリエント) | |
| ナイアシンアミド | 整肌・透明感&ハリ弾力サポート | ★ |
| ビニルジメチコン | 調整 | |
| マカデミア種子油 | 油脂(エモリエント) | |
| ステアリン酸グリセリル | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| ペンチレングリコール | ベース(保湿・抗菌) | △ |
| セイヨウノコギリソウ油 | 精油(香料) | |
| ドクダミエキス | 植物エキス(整肌) | |
| セイヨウヒイラギ葉エキス | 植物エキス(整肌) | |
| 1,2-ヘキサンジオール | ベース(保湿・抗菌) | |
| リンゴ酸ジイソステアリル | エステル油(エモリエント) | |
| 水添野菜油 | エモリエント | |
| ポリメチルシルセスキオキサン | 調整 | |
| ミツロウ | ロウ(調整) | |
| オリーブ油脂肪酸セテアリル | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| オリーブ油脂肪酸ソルビタン | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| マデカッソシド | 植物由来成分(整肌) | |
| セイヨウキズタエキス | 植物エキス(整肌) | |
| 乳酸菌培養液 | 保湿・整肌 | |
| (アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | 合成ポリマー(乳化安定) | |
| ヒドロキシアセトフェノン | 防腐剤 | |
| パルミチン酸 | 高級脂肪酸(調整or石けん合成) | |
| ステアリン酸 | 高級脂肪酸(調整or石けん合成) | |
| ポリアクリロイルジメチルタウリンNa | 増粘 | |
| カルボマー | 合成ポリマー(増粘・乳化安定) | |
| キサンタンガム | 多糖類(増粘) | |
| 水添ポリデセン | 炭化水素油(エモリエント) | |
| トロメタミン | ph調整 | |
| カラメル | 天然色素(着色) | |
| メリアアザジラクタ葉エキス | 植物エキス(整肌・製品の抗菌) | |
| DNA | 整肌 | |
| メリアアザジラクタ花エキス | 植物エキス(整肌・製品の抗菌) | |
| アデノシン | ハリ弾力サポート | |
| イソステアリン酸ソルビタン | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| アシアチコシド | 植物由来成分(整肌) | |
| EDTA-2Na | キレート | |
| ツボクサ葉エキス | 植物エキス(整肌) | |
| コクシニアインディカ果実エキス | 植物エキス(保湿・製品の抗菌) | |
| トリデセス-10 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| パンテノール | 整肌 | |
| コハク | ? | |
| ナス果実エキス | 植物(保湿) | |
| エチルヘキシルグリセリン | 保湿・抗菌 | |
| ウコン根エキス | 植物エキス(整肌) | |
| カミメボウキ葉エキス | 植物(整肌・製品の抗酸化) | |
| サンゴモエキス | 海藻エキス(保湿・製品の抗酸化) | |
| ワサビノキ種子油 | 油脂(エモリエント) | |
| ラベンダー油 | 精油(香料) | |
| ベルガモット果実油 | 精油(香料) | |
| トコフェロール | ビタミンE(整肌・製品の抗酸化) | |
| 塩化Ca | 保湿 | |
| 硫酸Mg | 保湿・めぐりサポート | |
| アシアチン酸 | 植物由来成分(整肌) | |
| マデカシン酸 | 植物由来成分(整肌) | |
| ツボクサエキス | 植物エキス(整肌) |